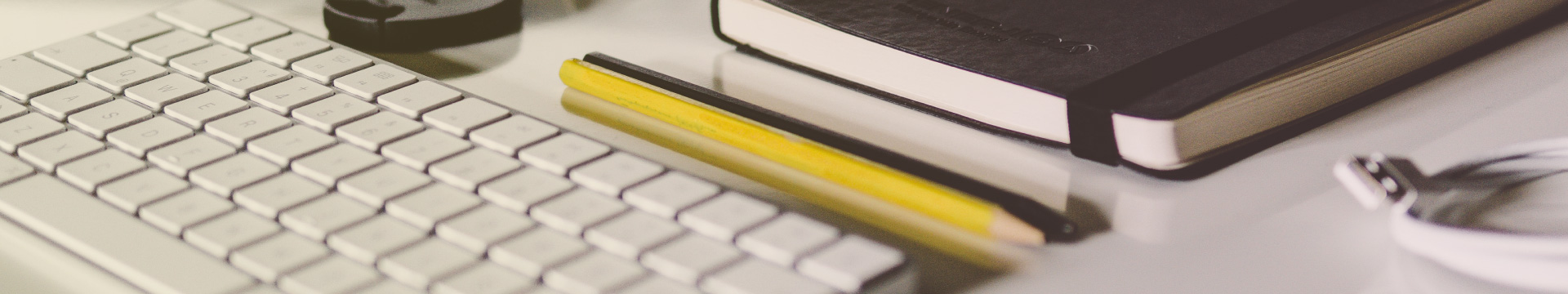
おしらせ&コラム
2025.4.28
製造業の最適な人件費率とは?業界平均と削減方法を解説!
利益を出しやすい企業なのかを見る際に大事な指標として挙げられるのが、人件費率です。
製造業において人件費率の最適化を図ることで、安定した収益を確保しながら企業成長につなげていくことができます。
本記事では、以下の内容をまとめました。
・製造業の人件費率の平均は?
・製造業の人件費率を最適化させるべき理由は?
・製造業の人件費率が高すぎる場合・低すぎる場合のメリットデメリット
・製造業の人件費率を最適化する方法は?
ぜひ最後までご覧ください。

製造業の人件費率の平均は?
製造業における人件費率は、売上高人件費率と売上総利益人件費率などが挙げられます。
売上高人件費率で見た場合、調査対象となった製造業4,671社の平均は34.6%でした。参照:日本政策金融公庫「(1)業種別経営指標」
このうち、黒字で自己資本のプラスの企業に限ると平均31.7%となっています。
一方、東京産業労働局が調査したデータでは、製造業594社における人件費率は31.4%と算出されています。参照:東京都産業労働局「東京都中小企業業種別経営動向調査報告書令和元年度調査(平成30年4月期~平成31年3月期決算) 」
このうち、黒字企業は29.9%、赤字企業は40.0%となっており、平均で出される数値よりも黒字企業は若干低めの人件費率であることが明らかです。
2つの指標からも製造業で黒字を目指す際に設定すべき人件費率は30%前後であることがわかります。
製造業の人件費率を最適化させるべき理由は?
そもそもなぜ製造業の人件費率を最適化させないといけないのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
本項目では、製造業の人件費率を最適化させるべき理由についてまとめました。
収益性を高められる
人件費率の最適化を目指す理由として、まず最適化を図れば収益性を高められる点が挙げられます。
製造業において人件費は固定費の中でもかなり比重を占めるものです。
ゆえに人件費を適正な範囲で収めていることは、固定費の安定につながり、収益性の向上につながりやすくなります。
人件費をカットすることで固定費を減らしつつ、その分を研究開発や設備投資に回すことも可能です。
企業を成長させて収益性を高めるという観点においても、人件費率の最適化は大事な要素となります。
競争力の強化につながる
製造業においてライバルに打ち勝つには、品質の高い製品を作り続けることが重要です。
それに加えて、ライバル同士の価格競争に競り勝つことも求められます。
コストを削減しつつ高品質を維持することが、企業が持つ競争力につながるのです。
この時、人件費率が適正であれば、製造コストを抑えた上で品質の高い製品を作りやすくなります。
人件費をカットし、商品開発に投資することによっても、競争との差別化を図ることは可能です。
また、業務の効率化も重要な要素であり、少ない人員でより多くの生産を確保する生産性の向上も競争力に直結します。
経営リスクを軽減できる
人件費率を一定に抑えることで、経営リスクの軽減にもつなげられるのです。
製造業に限らず、企業は景気の変動に左右されやすく、受注が減少した際に企業経営を圧迫する恐れが出てきます。
特に、製造業は景気の変動に大きく左右され、需要の変化が生じやすい産業でもあります。
万が一不景気になっても簡単には揺るがない企業を目指すには、なるべく人件費率の高騰を抑えることが大前提となるでしょう。
製造業の人件費率が高すぎる場合・低すぎる場合のメリットデメリット
製造業において黒字を目指すのであれば、おおむね30%前後が理想と言えます。
では、その30%よりも高すぎたり低すぎたりした場合にはどのようなメリット・デメリットがあるのか、気になる方もいるはずです。
本項目では、製造業の人件費率が高すぎる場合・低すぎる場合のメリット・デメリットについてまとめました。
製造業の人件費率が高すぎる場合のメリット
人件費率が高すぎる場合、従業員に対して賃金を多めに払うことができます。
そのため、同業他社と比べても優秀な人材を確保しやすくなると言えるでしょう。
高い年収の企業を求めて有望な人材が転職しようと動くため、技術力の高い人材を確保したい場合に、人件費率の高さが功を奏する場合もあります。
他にも従業員のモチベーションの向上や安定した長期雇用もしやすくなる分、ベテラン社員から若手社員に対して技術を継承しやすくなるのもメリットです。
製造業の人件費率が高すぎる場合のデメリット
人件費率が高いデメリットは、何と言っても利益率の低下につながりやすい点です。
人件費率が高ければ、その分固定費が増えるため、利益は低下しやすくなります。
また、固定費が増えることは余裕をもって使える資金が少なくなる可能性を意味しており、設備投資などに使う資金が減り、企業成長のスピードが落ちる可能性もあります。
製造業の人件費率が低すぎる場合のメリット
人件費率が低い場合のメリットは、利益率の向上や設備投資などへの資金の振り分けがしやすくなる点です。
大企業でも、人件費増が影響して利益を大幅に減らすケースは珍しくありません。
そのため、利益を確保する観点から、人件費を始めとする固定費削減に力を入れる企業は多いと言えます。
人件費率が低い企業は、売り上げを増やせば利益に直結しやすく、大きなメリットの1つとなっています。
製造業の人件費率が低すぎる場合のデメリット
人件費率が低い場合、人材が流出しやすい点が大きなデメリットです。
収入が少ない中で過剰な労働を強いられると、従業員のモチベーションは自然と落ちていきます。
すると、生産性の低下、品質の悪化につながるほか、労働環境も悪くなりやすく、技術が継承されにくくなるなどの懸念点も挙げられます。
製造業の人件費率を最適化する方法は?
現状の人件費率が高すぎる、もしくは低すぎるという企業も少なくありません。
では、こうした企業が人件費率の最適化を図るにはどうすればいいのか、本項目ではその方法をまとめました。
業務の効率化を図る
業務の効率化は、製造業の人件費率を最適化する上で一番基本的で、重要な施策の1つです。
無駄な作業をなくすことで、限られた人員でより多くの生産を行えるようになります。
例えば、リーン生産方式・トヨタ生産方式などを導入することで、不必要な工程や在庫の削減が可能です。
また製造工程において生じているボトルネックを特定することも、業務効率化につながります。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
人件費率の最適化にはDXの推進も欠かせません。
単純作業を自動化しつつ生産性を高めていくにはAIやIoTの活用は必須です。
自動化を推進することで、少ない人数で複数の工程を管理することができ、労働力の最適化が実現します。
そのためには、DXの導入・推進は欠かせない要素なのです。
人材戦略の見直しを目指す
人件費率の最適化には人材戦略の見直しもポイントとなります。
適正な人員構成と生産性を高める努力を重ねていくことで、過度な人件費の高騰を防ぎつつ、生産性を高められます。
例えば、ジョブローテーションを導入することで、従業員一人一人のスキルが向上し、複数の業務を行えるようになります。
すると、さまざまな業務に誰でも対応しやすくなるため、より柔軟な人材活用につながるのです。
加えて、成果主義の評価制度を導入していくことで、従業員のモチベーションを落とさずに、人件費率の最適化を目指しやすくなります。
まとめ
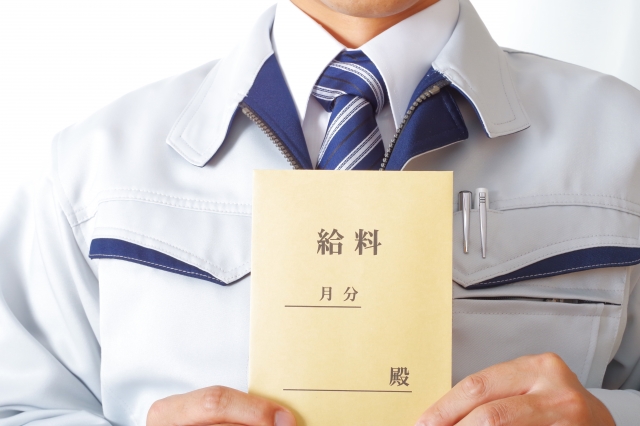
製造業の最適な人件費率は、30%を目安にするのが理想である一方、企業によっては20%台で抑えているケースもあります。
従業員のモチベーションを下げずに人件費率を落とせるかが、大きなポイントと言えるでしょう。
30%以上の人件費率が常態化している企業は、なぜ高止まりしているのかの分析を行い、人件費率の最適化を図ることをおすすめします。
Contact
お問い合わせ
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームはこちら
local_post_office お問い合わせ
